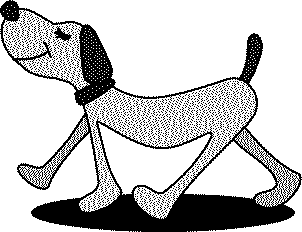
外は思いのほか暖かく、雨の割にはコートがいらないほどだった。
こんな日は、ついつい傘の柄を、くるくる回してしまいたくなる。
くるーり。
くるるん。
水色の傘は、頭上で、くるくると回転した。
雨は、嫌いじゃない。
水色の長靴も、ぴちぴちステップを踏む。
背中のランドセルも振り子のようにゆれて、中の筆箱や教科書たちも、カタカタ
踊る。
「あっめあっめふーれふーれ、かーあさーんが・・・♪」
口をついて出てくる、こんな歌も、気分よくはずんでしまう。
・・・ん?
なにか、いた?
道の脇には、定間隔におかれている並木まがいの人工的電柱と標識が、群を
連ねているが、ある三行広告の貼られている電柱の陰から、なにか動いたよう
な気がしたのだ。
僕は、そうっと、長靴が鳴らないように、近づいて行った。
そして、見つけたのだ。
その、電柱と同色をした灰色がかったその子犬をー。
「きゅーん・・・」
それが、彼女ーたろうーとの運命の出会いとなった。
愛らしく見つめる、そのつぶらな瞳に、僕は、心を奪われてしまったのだった。
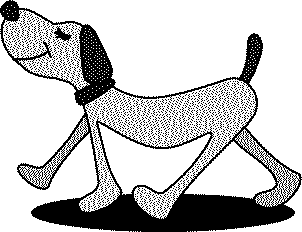
プロローグ
